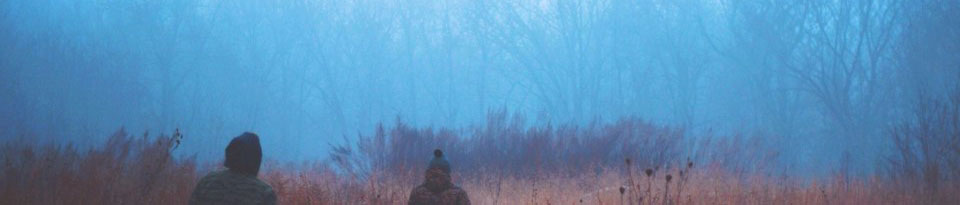まずそのまえに
音声っていうのは空気の振動なんだ。それが耳に入って鼓膜を震わせて、神経を通って脳に信号が伝わって言葉としてとらえられる。
ところで、電話をとって、声を聞いただけで相手が誰だかわかることはないかい?声だけで男か女かわからないかい?声だけで子供か、大人か、年寄りか、もしかしたら40さいくらいとかもわからないかい?声ってみんな違うんだ。空気の振動はみんな違うんだ。
でも、とっても不思議なことがある。だれが言った「おはよう。」でも「おはよう。」って聞こえるんだ。一人ひとりの声、空気の振動はみんな違うのに、脳に入ると誰が出した声でも「おはよう。」って聞こえるんだ。
物理的な音、つまり空気の振動と、脳で捉えた言葉としての音声は同じではないんだ。逆もそうだよ。同じだと思って発音している音声は必ずしも同じ音ではないんだ。たとえば「新田」。しんでんの「ん」は舌が歯茎に付いていないかい?では、「新橋」は?しんばしの「ん」は唇が閉じていないかい?時間があったら新橋駅に行ってごらん。ローマ字だと「SHIMBASHI」って書いてあるはずだよ。物理的には「新田」の「ん」は「なねの」、「新橋」の「ん」は「まめも」と同じ音なんだ。でも、日本人の脳にとってはどっちも「なねの」でもなければ「まめも」でもない「ん」って聞こえるんだ。
ちなみに、日本語の「ん」にはもう1つある。「新宮」、しんぐうの「ん」は唇は閉じないし舌も歯茎には付かない。日本語の「ん」は物理的には大きく分けると3種類あるけれど、脳ミソが理解する心理的な音は「ん」の一つだ。
脳で理解する音声と空気の振動の音は必ずしも同じではない。耳で聞いた音を脳が音声として理解するのだけれど、音のどういう特徴に重きを置いて音声としてどのように分類していくか、英語と日本語では違うんだ。
音声の4つの側面
音声って、以外に不思議だろ?まず、取っ掛かりだけど、英語の音声が日本語と違うところを4つの側面で考えてみよう。
発音記号
まず、発音記号。これは避けては通れない。もちろん、日本語と英語の音声の違いを語るとこれが大部分を占めてしまう。
日本語だったらさしずめ50音、濁音とか撥音とかをふくめて本当に50なのか数えたことはないけれど、多分、日本語ではこれくらいしか使っていないのだろう。口の開け方を変えたり舌の筋肉を使いこなしたりするともっといろんな音を出すことができるのだが、日本語ではこれくらいしか使わない。
英語は日本語とは違う音を使う。英語の発音記号はあるものは日本語とほとんど同じだし、あるものは日本語では全然使わない音だし、またあるものは似ているんだけれども微妙に違う。英語からしてみたら「日本語はこんな音もあるの?」というのもある。日本語と英語では、脳が理解して分類をしている音声のセットが違うんだ。この違いは複雑でたくさんあるので、別のところで説明をする。
残りの3つは音の高さと長さと大きさ。これを知っていることが意外に大事。
音の高さ
「毎日新聞を読む」を声に出して言ってみよう。どういうふうに言った?
東京ではだけれど、「毎日、新聞を読む」と言った人は「毎日」の「ま」を高い声で言わなかったかい?
朝日でも読売でもなくて「毎日新聞を、読む」と言った人はいないかい?きっと、「新聞」の「し」を高い声で言ったはずだ。
日本語は音の高低が大切で、これをあやつることで意味が変わることがある。「飴」と「雨」、「1」と「位置」、「梅雨」と「汁」、いろいろあるよね。意味は変わらないまでも音の高低を変なふうにしてしゃべると「えぇ?」と思われる。「なまり」があると思われたり、時には通じなくて聞き返されることもある。
一方で英語はどうかといえば、英語では音の高低は大切ではない。むしろ、英語では音の高低は変えないで、フラットに同じ高さの声で話すんだ。
英語も音の高低を変えることはあるよ。でも、その変え方が日本語とは少し違う。日本語は波のようになめらかにグニャグニャと音の高低を変えながら話す。英語の場合は低い声から高い声、あるいは逆に高い声から低い声に、スパッと切り替えてしまうことが多いんだ。
日本人は英語を話すときも日本語のクセで話してしまう。まあ、これは当たり前のことなのけれど、これが日本人の話す英語がダサく聞こえるポイントの一つなんだ。日本人は英語をしゃべるときもグニャグニャと音の高低を変えてしまって、これがいかにも日本人っぽい。
英語の練習をするときは音の高さは変えないでフラットに話すようにしよう。
音の長さ
日本語は音の長さも大切。「おばさん」と「おばーさん」、「おじさん」と「おじーさん」。音の長さで意味も変わる。
英語はどうかというと音の長さ自体はそれほど大切なものではないんだ。
bit と beat はみんなはどういうふうに発音する?bit (ちょっぴり) は「ビット」、beat は日本語になってしまってるね、「ビート」かな?発音記号だと bit は /bit/ で /i/ は短母音の「イ」、beat は /bi:t/ で /i:/ は後ろに : が付いているから長母音の「イー」って習った人もいるかもしれない。でも、これは必ずしも正しいわけではない。どちらかというと英語の音声を日本語のものさしで分類しようとしている。
英語の脳では bit と beat は違いはその長さで分けているのでははなくて、音そのもの違いに着目している。beat のほうは日本語の「イ」と比べるとほっぺたに力を入れて唇を左右に引っ張って、舌も高い位置で上あご (口の中のてんじょう) に近づける。bit のほうはほっぺたはもっとダラっとして日本語の「イ」と「エ」の中間、むしろ「エ」に近いくらいの音なんだ。
確かに bit よりも beat の方を長く発音する傾向はある。でも bid (/bid/、入札のこと) と bead (/bi:d/、ビー玉のビー、複数形にするとビーズだよ) を加えて4つの長さを比べるとどうなると思う?一番短いのは bit で一番長いのは bead だ。beat と bid はその間で、どっちが長いかというと長母音の /bi:t/ も短母音の /bid/ もどっこいどっこいでたいした差はなくなる。秘密は次にくる音だ。/t/ は無声音で声帯は震えない、/d/ は有声音で声帯が震える。声帯が震えない音は震える音よりもエネルギーが必要なんだ。/t/ は /d/ よりもエネルギーが必要な音なので、それに備えて省エネで前の音を短くしてしまうんだ。これは英語の単なるクセなんだ。日本語みたいに長いとか短いとかを意識しているわけではない。
英語でも長く発音しなければならないところと短く発音しなければならないところはある。それはつぎの音の大きさと英語のリズムに関係があるんだ。
音の大きさ
英語では音の強弱が大切なんだ。「ストレス」とか「強勢」とかって習っていないかい?発音記号で上に 「ˈ」みたいのが付いているやつだ。/ˈingliʃ/ (English) だと「エングレシュ」みたいに最初の /ˈi/ を強く発音する。
「『ˈ』がついてたら大きな声で読めばいいの?そんなの簡単じゃん。」って思うだろ?それがそうでもなくて、けっこう厄介なことなんだ。
アクセント
どの言語にとっても心地のよい抑揚っていうのがあって、これを間違えると意味がわからなくなってしまうことがある。さっきの「まいにちしんぶんをよむ」もそうだけど、「にわにわにわとりがいる」もイントネーション次第で「2羽庭には鳥がいる」にも「庭には2羽鳥がいる」にも「庭にはニワトリがいる」にもなるし、そのパターンを外れてしまうと何を言っているのかわからなくなることもある。
日本語だとひらがな一文字が1拍、長音は2拍でリズムをとって、あとは音の高低で日本語の心地よさを作っている。それでは英語はどうかというと、英語は音の大小・強弱で抑揚をつけていて、強い音が同じ間隔で現れるようにリズムをとっているんだ。
これを読んでいるみんなは、生まれてから少なくても10年以上は日本語を聞いて話しているはずで、日本語の抑揚に慣れてしまっている。何も考えなくても何かを喋れば日本語になるし、逆に、外人のしゃべる日本語を聞けばすぐに日本人ではないことがわかるんだ。英語であっても日本語の抑揚で喋ろう、聞き取ろうと、筋肉も脳もクセがついてしまってるんだ。
まず、日本人が英語を喋ると音の強弱を音の高低に置き換えてしまう。音の高低をグニャグニャと波打って変えてしまうので、これがチョーダサいしカッコ悪い。
次に、日本語では1拍ごとに1音節、つまりひらがな1文字が聞こえるというリズムで待ち構えるので、外人の話す英語に追いついていけなくなる。英語では強い音にビートを合わせて同じ間隔で話すんだ。強い音と強い音の間にどれだけ弱い音があるかは一定じゃない。弱い音がたくさんあればそこは早口になるし、発音もいい加減になるんだ。
ちなみにだけれど、ある人は英語の音の強弱が「アクセント」って教えてもらったかもしれない。またある人は「アクセント」は英語では「方言」とか「訛り」とかの意味で、「ストレス」または「強勢」というのが正しいんだと教えてもらった人もいるかもしれない。ここでは「アクセント」っていうのは言葉の抑揚と思って。音の高低・音程の変化で抑揚をつける言語もあれば音の長さに変化で抑揚をつける言語も音の大小・強弱で抑揚をつける言語もある。英語は音の大小・強弱で抑揚をつける言語で、英語では「アクセント=強勢・ストレス」だということにしよう。
強く発音する場所って?
単語の中では発音記号の上に強勢の記号の「ˈ」がついているところだ。ある程度のパターンはあるけれど、結局は地道に一つ一つ調べて覚えるしかないね。覚えるっていっても、べつに発音記号と強勢の記号を正しく書くことができるようになれといっているわけではない。卓球の素振りと一緒で、口の筋肉が覚えて正しく発音できるようになればよい。
もう一つここでみんなに知ってほしいことは、英語ではすべての単語を強く発音するわけではないということなんだ。英語の文では強く発音する単語とそうではない単語がある。なので、強く発音する単語の強勢のある場所を強く発音するということになる。
単語は大雑把に「内容語」と「機能語」の2つに分ける分類の仕方がある。雑な説明だけれど、「内容語」というのは意味のある単語で、名詞、動詞、副詞、形容詞、疑問詞なんかだ。「機能語」というのは意味的には重要な情報のない単語で、代名詞、助詞、前置詞、冠詞、接続詞、関係代名詞、be動詞なんかだ。基本のルールだけれども、「内容語」は強く発音をする。逆に、「機能語」は強く発音をしないんだ。
たとえば “I learn pronunciation.” という文を例にする。pronunciation はここのテーマの「発音」のことだよ。learn はいいよね、「勉強する」だ。動詞の learn と名詞の pronunciation が内容語だから強く発音をする。pronunciation は発音記号で書くと /prənənsiˈeiʃn/ で /ˈei/ のところだけを強く発音する。I は代名詞で機能語だから強く発音はしない。だから「アラムパ(ラ)ナンツエイシュン」のように発音をするんだ。
「/ə/ ってなに?」とか「learn がラム? 」とか疑問はいろいろあると思うけれど、それはおいおい説明するよ。単語は「内容語」と「機能語」に分けることができて、「内容語」は強く発音するけれども「機能語」は強く発音しないのが基本ということをおさえて。「内容語」でも強く発音をしないこともあるし、例文でも「アンタじゃなくてアタシが」みたいなときなんかは I を一番強く発音する。でも、まず基本。強く発音するところは強く発音する、弱く発音するところは弱く発音する。これが日本語と違うところだ。
強い音を同じ間隔って?
ここで新情報なのだけど、英語で「強く」発音するということは、それは同時に「長く、はっきりと」発音をするということなんだ。逆に、「弱く」発音するということは「短く、早口に」なる。
まずはさっきの例文だ。
“I learn pronunciation.” (「アラムパ(ラ)ナンツエイシュン」)
ちょっと極端に「ラム」のところを「ラーーム」くらい、「エイ」もそれくらいの長さで、反対に弱く発音するところ、特に真ん中の「パ(ラ)ナンツ」のところを早口に発音してみようか。それが英語のいリズムなんだ。
少し複雑にしよう。例文に飾り付けして “I should have learned English pronunciation.” にするよ。
「should have + 過去分詞」なんて習ってないって?ごめん、でも、全然難しくないよ。「〜しておけば良かった」だ。だから “I should have learned English pronunciation.” は「英語の発音、勉強しときゃよかった。」だよ。
この飾りつけしたほうでも強く発音するのは learn と pronunciation の2か所だ。English は「英語の」っていう形容詞で内容語なんだけれど、形容詞が前の方から後ろの名詞を修飾するときは普通は後ろの名詞の方を強く発音して、形容詞は強く発音しないんだ。これも追々。
で、どうなるかというと「アシャラヴランデングレシュパ(ラ)ナンツエイシュン」のように発音をするんだ。
これも最初の例文のように極端に「ラン」のところを「ラーーン」くらい、「エイ」もそれくらいの長さで、反対に弱く発音するところ、特に真ん中の「デングレシュパ(ラ)ナンツ」のところを早口に発音してみようか。
例文を2つ並べてみるよ。
“I learn pronunciation.” (「アラムパ(ラ)ナンツエイシュン」)
“I should have learned English pronunciation.” (「アシャラヴランデングレシュパ(ラ)ナンツエイシュン」)
「強い音を同じ間隔」っていうのはこの2つ例文を同じリズムで発音することなんだ。一目瞭然で長さが全然違うけれど、できる?
強く発音する部分は長くはっきりと発音する一方で、弱く発音するところはいい具合にサボらないとならないんだ。I should have のところを「アイ シュッド ハブ」みたいなリズムで待っていると聞き取れないよ。それに、外人は「アイ シュッド ハブ」を単純に早回しにしているわけじゃないんだ。そもそもそんなふうには発音していないんだ。
“The doors on the right side will open.” いま、電車の中でこれを読んでいたらチョーラッキーだよ。「右手のドアが開きます。」だね。聞いてごらん。「ザドアズオヌゼライツアイドゥエルアウプヌ」みたいに聞こえない?強く発音するのは doors、right、side、open の4つだ。手をパン、パン、パン、パンって4回叩きながら、この4つを同じリズムで発音してみよう。英語っぽく聞こえないかい?right は形容詞で後ろの doors を前から修飾するので、基本ルールだと強く発音はしない。でも、今は右のドアが開くか、左のドアが開くかが重要なんだ。だから、right または left は強く発音するんだ。
もうひとつ、英語と日本語の違うところ
日本語って、じつは、喉で空気の流れをプツプツと切りながら話しているんだ。「声門閉鎖音」ていう立派な名前があって、発音記号もあるよ。[ʔ] って書くよ。声門というのは声帯がある場所のことで、声帯を閉じることで肺から出てくる空気の流れを切ってしまうらしい。見たことないけれど。
小さな「っ」がそれだね。「ざっし」と「あっさり」とかだよ。これはわりと意識的に言ってるんだけど、「あいうえお」の前とかも無意識のうちに実は小さく息を途切れさせることがよくある。「里親」と「砂糖屋」がよく例に使われる。(他にもうちょっとマシな例はないのかな?砂糖屋なんて街で見たことないだろ。)「さとおや」の「お」の前で小さく息を切ると「里親」になって、それを切らないと「砂糖屋」になる。これって、無意識だよね。他にも文の最後で息を切って終わらせたり、文の途中も区切りをつけたいときに小さく息を切ったり、日本語では無意識だけれどそれはたくさん使っているんだ。
英語ではこの「声門閉鎖音」をあまり使わない。というか、日本語ではおそろしくたくさん使う。だからそのクセがつい出ちゃう。apple の前では不定冠詞は a ではなくて an になって「アンナップル」になるんだったね?an orange は「アンノーレンジ」だよね?中学校の英語の最初の授業ではそう習うんだけど、キミの英語の先生はそう発音しているかい?みんなはどうだろう?簡単に「アンアップル」、「アンオーレンジ」って平気に言えていないかい?理由は2つあって、ひとつは an の「ん」を新田の「ん」ではなくて新宮の「ん」で発音しているから。もう一つはアップルの「ア」、オレンジの「オ」の前で声門閉鎖音を使って息を切っているからだ。逆に、アメリカ人に Kenich-san (「健一さん」) と呼ばせると「ケネチサン」みたいになるはずだ。
日本人が英語を話すときには息の流れを止めないことを意識をしたほうがいい。/p/、/b/、/t/、/d/、/k/、/g/ の6つの音は空気の流れを止めて出す音だ (これもおいおい説明するよ)。このときだけは息の流れを止めなければならない。けれど、それ以外はずっと息は止めずに出しつづけるんだ。英語を話すときは喉の奥の方を少し開くようにするといいよ。普段、日本語を話すときよりも少し声が低くて太くなるけれど、アメリカ人の話し方って、そんな感じしない?